NPO法人
はこだて街なかプロジェクト


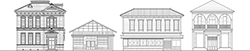
函館山麓から港に至る函館の旧市街・西部地区に、旧函館区公会堂をはじめとする国指定重要文化財の建物と並んで、歴史的町並みを築き上げた市井の人びとの建物がある。「上下和洋折衷」と呼ばれる独特の建築様式を持つ住宅や店舗である。
1901(明治34)年に建てられた小森家住宅店舗もその一つ。西部地区の建物は1907(明治40)年の大火でほとんどが灰と化したが、現在「弁天町」と呼ばれるこの一画だけが火災を免れた。家主の田中仙太郎は、海産商を営みながら奥の2階を貸間としていたという。貸間を有した店舗付き住宅は希である。
1階は大きな船具も搬出入できる「和風荒間硝子入り格子引戸」の店構え。店内からは格子越しに、通りを行きかう人の姿をうかがい知ることができる。玄関向かって右側の戸袋に雨戸を納め、左側は帳場。商談は帳場から階段を上った2階の和室で行った。2階の洋風縦長開き窓は港を向いている。商談の客は、和室に洋風窓という時代を先取りしたデザインに目を見張ったことだろう。
風待ちの港から
火災の多い町ゆえか、屋根は瓦屋根。重たげな屋根の軒は、雲形の持ち送りや軒蛇腹のシンプルな小壁で軽やかな表情になる。
田中仙太郎は日本海に面した兵庫県美方郡諸寄(もろよせ)の出身。露領・北洋漁業で好景気に沸く港町函館の活気にひかれて渡って来たのだろう。諸寄は岬がぐるりと内湾を抱え、江戸時代から明治にかけて北前船の「風待ち港」として栄えた港町だ。亡くなった船乗りを供養した寺が港を見下ろし、あらゆる路地は港へとまっすぐつながる。そんな故郷によく似た函館の一角に、田中は土地を購入したのだった。
当時の函館市は人口8万人余。1941(昭和16)年に太平洋戦争開戦で中止されるまで、露領・北洋漁業の一大出漁基地であった。
「田中仙太郎商店」は戦時中の1944(昭和19)年、海事工事を営む「吉見海事工業」に変わった。所有者の吉見与次郎は、仕事を通して田中の商店と取引があったらしい。吉見夫婦は1階で暮らし、2階では引き続き貸間を営んだ。そこで暮らした中に小森圭一がいた。
小森家は岩手県二戸市北福岡の出である。圭一の父明七は函館へ移住して漁業資材の販売会社に勤めた。住まいは現在の堀川町。その後宝来町で「海龍」という旅館を営み、更に弁天町付近で「西浜旅館」を開業した。息子圭一は父を追って函館に渡り、時計店で働いた。やがて弁天町の建物を吉見海事工業から借りて漁業資材や漁網の販売を始め、1950(昭和25)年、小森家はこの建物を買い取った。その2年後、10年間の空白を経て北洋漁業が再開され、函館の町は再び漁業関係者でにぎわい始める。
19才の田村キヨが、二戸から函館の小森家へ嫁いだのは翌53年のことである。
空き部屋を貸間に
「忙しくて忙しくて、休みなく夜遅くまで働きました。海のそばなので、上陸した船員が頻繁に店に来ましてね」とキヨは往時の活況を振り返る。小森夫婦は1階で生活し、2階は元の所有者の吉見夫婦。戦後の住宅難の時期であり、小森家もまた空き部屋を貸間とした。
北洋に独航船が出航する時期、店の前の通りは食材や生活必需品、作業資材などを扱う出店がぎっしりと並んだ。小森家も引戸を開け放って客を迎え入れ、隣の布団店「わたや」は布団の打ち直しに来る船員が引きも切らず。戦災で沈滞した函館のまちは、戦前の北洋漁業の最盛期を上回るほどに活気を取り戻した。雑貨屋、小さな飲み屋、銭湯などの店が立ち並び、路地には長屋が造られ、前浜には釣りをして遊ぶ子供の姿があった。
やがて日ソ漁業交渉がその熱気を冷まし、北洋漁業は終焉を迎え、西部地区の町並みの歴史の針は止まる。高度経済成長、そしてバブル経済の時期も、上下和洋折衷様式の小森家住宅店舗はそのまま残り続けた。現在は古い船の道具を扱うアンティークショップとして、羅針盤や霧笛、舵輪などがひっそりと佇んでいる。(敬称略)
「和と洋」折衷させた民衆の知恵
箱館(現函館)は江戸時代の中ごろに蝦夷地(えぞち)の主要港としての地位を確立し、幕末に開港して飛躍的に発展した。函館山山麓の西部地区には古くから市街地が形成され、函館の「発祥の地」となった。その歴史的町並みの中には、「上下和洋折衷」と呼ばれる独特の建築様式の建物が現存している。
1階は和風、2階を洋風とした住宅、店舗などである。なぜ上下和洋折衷にしたかは定かでないが、1878(明治11)年に開拓使長官一行がロシア極東ウラジオストクとの通商のため、現地を訪問したことと関係があると言われている。
極東の港町に似て
この訪問団には、函館支庁の官吏村尾元長ら函館の政財界関係者8人が含まれていた。ウラジオストクの1872(明治5)年の地図を見ると、街区街路は港に平行に、それと直交する街路は山から港に向かって真っすぐに造られている。村尾らは、函館とよく似て坂の多いこの港町の街並みを目に焼き付けていたはずだ。
訪問団がウラジオストクを訪ねた78年と翌79年、函館は続けざまに大火に見舞われた。陸繋島という独特の地形から強い海風が吹き渡る西部地区は、たびたび大火にさいなまれてきた歴史があり、火災との闘いが西部地区の都市景観の底流にある。明治初期のこの2度の大火を受けて、函館支庁は火災に強いまちへと街区改正を検討した。蛇行した主要街路を直線的にし、道路の拡幅とともに防火を意識したまちづくりが計画されたのだが、このとき村尾ら官吏の脳裏にはウラジオストクの街並みが思い浮かんでいたのではないか。街区改正後の函館の街路の骨格は、ウラジオストクにきわめて近いものとなった。
2度の大火の罹災者の中には、村尾とともにウラジオストクを訪れた金森森屋洋物店の渡邊熊四郎がおり、また渡邊と同様に洋物商を営んだ平田文右衛門ら函館の財界人がいた。渡邊らはウラジオストクで傾斜地に建つペンキ塗りのカラフルな洋館を見ていたはずで、函館山山麓の民家の2階部分を洋風に造り、ペンキを塗ることを考えても不思議ではない。それだと港から函館山を見上げた時に、家々の2階の壁が綺麗に並んで見える。
棟梁たちの創造力
このころ、日本の洋風建築のほとんどは大工によって造られ、瓦屋根が基本だった。函館の上下和洋折衷様式の建物も同様である。この様式の店舗の1階部分では、人の往来や店への出入りが見やすいよう、太い格子を粗く組んだ「荒間格子戸」に透明なガラスを入れた建具を、通りに面した出入口など大事な部分に配した。住宅の場合は、中をのぞかれないよう型板ガラスや細かな格子を用いた。
屋根の軒や1階の庇(ひさし)の下には、荷重を支える「持ち送り」と呼ばれる木材や鋳物でできた部材を取り付けた。外壁は板を横に張り、窓は縦長の開き窓か、上げ下げ窓。窓枠や柱は彫刻が施され、異なる色のペンキで壁と塗り分けた。
1階と2階、また和風の屋根と洋風のデザインの切り替えには、装飾的な木材の帯状の部材「蛇腹(じゃばら)」を水平に取り付けた。壁の各層を区切る部分に取り付けた蛇腹は、位置によって軒蛇腹、胴蛇腹、天井蛇腹と呼ばれる。
旧函館区公会堂など函館における本格的な洋風建築は、役所が招へいした外国人技師や、彼らから建築を学んだ日本人によって造られた。一方で、上下和洋折衷様式の「庶民的建築」とでも言うべき住宅や店舗の大半は、地元の大工棟梁の経験と知恵と創造力によって造られたのである。
濃密なコミュニティー
小森家住宅店舗は函館市弁天町の埋め立て地に建っている。露領・北洋漁業の盛んな時代、この建物の目の前は海だった。1945(昭和20)年の終戦後まもなく小森圭一が建物を借りた時は、さらに先まで埋め立てられ、今も残る倉庫群が建ち並んでいたという。「それでも海は今よりも少し手前にあった」と、圭一の息子健良(たけよし)は話す。
小森圭一は7人兄弟の長男。弟たちの面倒を見るためにこの建物で懸命に働き、子供を育てた。圭一が建物を借りた時は貸間も含め6家族が同居し、便所や流しは共同、風呂は無く近くの銭湯を利用したという。当時、風呂のある家はごくまれで、銭湯は人々のコミュニケーションの場だった。地域には函館ドック(現函館どつく)の従業員や船員、商店主とその家族が、長屋や借家、貸間にびっしりと暮らし、濃密なコミュニティーを形成していた。
この弁天町界隈にあった映画館や射的場、宿屋、遊郭など、往時の賑わいを支えた建物や場所は既に無く、前浜で遊ぶ子どもの姿も見かけない。建物の所有者は移り変わり、建物とまちの記憶をたどるのは難しくなっている。西部地区の繁栄を見続けた「田中仙太郎商店」が、その来歴とともに将来へ引き継がれることを願わずにはいられない。(敬称略)



